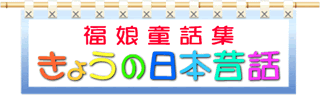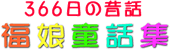福娘童話集 > きょうの日本昔話 > 1月の日本昔話 >大力の坊さん
1月18日の日本の昔話
大力の坊さん
京都府の民話 → 京都府情報
・日本語 ・日本語&中国語 ・客家語
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 「ひつじも眠る朗読チャンネル」
【本気で眠りたいあなたへの睡眠朗読】日本昔話集ぐっすり眠る
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 ナレーター熊崎友香のぐっすりおやすみ朗読
【大人も子供もぐっすり眠れる睡眠朗読】心ふんわり軽くなる日本昔ばなし特集 元NHKフリーアナ
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
制作: フリーアナウンサーまい【元TBS番組キャスター】
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 「眠りのねこカフェ」
※本作品は、読者からの投稿作品です。 投稿希望は、メールをお送りください。→連絡先
投稿者 「眠るうさぎのささやく読み聞かせ」
| ♪音声配信(html5) |
| 音声 ヤマネコギン |
| ♪音声配信(html5) |
| 朗読 : stand.fm 「癒しの森 朗読セラピー」 |
むかしむかし、比叡山(ひえいざん)の延暦寺(えんりゃくじ)に、実因僧都(じついんそうず)という坊さんがいました。
広く仏教について勉強をしたとても偉い坊さんでしたが、この人は、とても力持ちの坊さんとして有名でした。
これは、その実因(じついん)のお話です。
実因が、昼寝をしていた時の事です。
若い元気な弟子たちが師の力の強さを試そうと思い、クルミを八つ持って来て実因の足の指の間に一つ一つ挟んだのです。
(・・・おや?)
実因はそれに気がついたのですが、わざとタヌキ寝入りをして、弟子たちのするのに任せていました。
しばらくして、「ううーん、よく寝たわい」と、
力を入れてのびをすると、クルミの実が八つともバリッと砕けてしまったという事です。
さて、その実因が、宮中(きゅうちゅう)で行われたご祈祷に呼ばれた事がありました。
それが終わると他の坊さんたちは帰って行きましたが、話し好きの実因はそこに残って色々と話し込んでいるうちに、すっかり夜もふけてしまいました。
「遅くなったな。さて、帰るとするか」
実因は、やっと立ち上がりました。
周りを見回しましたが、どこに行ったのか、お供の坊さんの姿が見えません。
ただ履き物が、きちんと並べてあるばかりです。
「どこへ行ったかな?まあ、いいか」
実因は履き物をはいて下に下りると、秋門(しゅうもん)から外に出ました。
外といっても、ここはまだ御所の内です。
ちょうど、明るい月が出ています。
「いい月だ、少し歩いてみよう」
ふらふらと歩き出すと、どこから忍び込んできたのか一人の男が現れました。
そして実因の姿を見ると、すたすた歩み寄って来て、
「これはお坊さま。お供も連れず、どちらにおいでですか?さあ、わたしの背中におぶさりなさいませ。どこなりと、お連れいたしましょう」
と、声をかけました。
そこで実因は、「それは、ありがたい」と、その男におぶってもらいました。
男は実因をおぶると、どんどん歩き出しました。
体の大きな、とても元気そうな若者です。
まるで走る様に御所を出ると、左に折れてしばらく行って立ち止まりました。
「さて、ここで、降りて下され」
男は実因を背中から降ろそうとしましたが、実因は、
「こんな所へ用はない。わしは、お寺の学寮(がくりょう)へ行こうと思っていたのじゃ」
と、平気な顔で答えて、降りようとしません。
「何だと!」
男は、実因が怪力の持ち主である事を知りません。
立派な着物を何枚も重ねて着た普通の坊さんだと思っていたので、脅かしてその着物を奪い取ってやろうとしたのです。
「この坊主め! 命がおしけりゃ、さっさと着物を脱いでいけ!」
しかし実因は、落ち着いた声で言いました。
「なるほど、着物が目当てとは知らなかった。
てっきり、老人のわしが一人歩きをしているのを見て可愛そうに思い、こうしておぶってくれたのだとばかり思っていたわい。
しかし、この秋の夜ざむに着物を脱ぐわけには」
そう言いながら実因は、左右の足で男の腰をぎゅっと締め付けました。
その力はあまりにも強く、まるで腰がちぎれる様な痛さです。
「ああっ! いて、て、て。このくそ坊主! 早く降りやがれ!」
「くそ坊主?」
実因は、いっそう足に力を入れました。
「いや、その、・・・お坊さま」
男は、泣きそうな声で謝りました。
「お坊さま、私が悪うございました。考え違いをしていました。
お坊さまの着物をはぎとろうなど、わたしが馬鹿でございました。
この上は、どこへなりともお供いたします。
ですから、ですからどうか、腰を、腰をちょっとお緩めになってくださいませ。
このままでは、本当に腰が折れてしまいます」
「何だ、若いくせにだらしない奴め」
実因は、腰を緩めてやりました。
すっかり観念した男は、実因を背負いなおすと小さい声で尋ねました。
「あの、どちらへ、おいででございましょうか?」
「うむ、えんの松原へ行ってくれ。わしはあそこで月を見ようと思っていたのに、お前が勝手にこんな所におぶって来たのじゃ」
「はい。では」
男は実因をおぶったまま御所に引き返して、えんの松原に連れて来ました。
「あの、着きましたので、お降りになって下さいませ。わたしはここで失礼します」
しかし実因は降りようとはせず、
「ああ、いい月だ」
と、言って、月をいつまでも眺めています。
「あの、どうかお降りになって」
男は頼みましたが、しかし実因は知らん顔で言います。
「次は、右近の馬場へ言ってみたい。そこへ連れて行け」
「あの、そこまではとても。どうか、お許し下さい」
「右近の馬場だ」
実因は、また足に力を入れました。
「あ、いて、いて。分かりました。参りますから、ご勘弁を」
男は仕方なく、もう一度実因を背負い直すと御所の外に出ました。
そして右に曲がり、やっとの事で右近の馬場にたどり着きました。
しかし、そこでも実因は降りようとせず、月を眺めたり歌を詠んだりしていました。
「さて、次は喜辻(きつじ)の馬場(ばば)を、下の方へ散歩してみたい。連れて行ってくれ」
男はへとへとですが逆らう事が出来ず、ため息をつきながらそこまでおぶって行きました。
そしてその後は、西宮(にしのみや)へも行きました。
こうしてその男は実因を一晩中おぶい続けて、夜明け頃、やっとお寺の学寮に送り届けたのです。
実因は奥に入ると、一枚の着物を持って出て来ました。
そして、疲れ切って動く事が出来ない男に、その着物を与えると、
「これは駄賃だ。持って帰れ。・・・だが、次は許さぬから気をつけよ」
と、言って、奥に入って行きました。
おしまい
| 1月18日の豆知識 366日への旅 |
都バス記念日 |
パフィオペディルム(Paphiopedilum) |
| きょうの誕生日・出来事 1947年 ビートたけし(タレント) |
| 恋の誕生日占い 自分の考えをしっかりと持った |
| なぞなぞ小学校 空を飛べないチョウは? |
| あこがれの職業紹介 お茶インストラクター |
| 1月18日の童話・昔話 福娘童話集 |
| きょうの日本昔話 大力の坊さん |
| きょうの世界昔話 ホジャおじさんのこの世の終わり |
桜島大根汁 |
| きょうの日本民話 2 宝箱をとりもりどしたネコ |
| きょうのイソップ童話 泉のほとりのシカとライオン |
| きょうの江戸小話 金の鳥居(とりい) |
| きょうの百物語 ニンジンの始まり |
福娘のサイト |
||||||
| 366日への旅 毎日の記念日などを紹介 |
||||||
| 福娘童話集 日本最大の童話・昔話集 |
||||||
| さくら SAKURA 女の子向け職業紹介など |
||||||
| なぞなぞ小学校 小学生向けなぞなぞ |
||||||