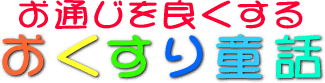福娘童話集 > お薬童話 > お通じを良くするお薬童話
クモおんな
むかしむかし、とっても気の強いひとりのお坊さんがいました。
そのお坊さんは、チンカンチンカンと、かねをたたきながら、村から村へ旅をして歩くお坊さんです。
ある日の夕がた、お坊さんが、山をおりて小さな村里に入ったとたん、雨がふってきました。
かまわずぬれて歩いていましたが、そろそろ日もくれようというのに、雨はぜんぜんやみません。
お坊さんは、近くのお百姓(ひゃくしょう→詳細)の家の戸口にたって、頭をさげると、
「この雨でなんぎしております。どうかひとばん、とめてくださるまいか」
「へえ、とめてあげてえのはやまやまだども、あいにく今夜は客があってなあ」
その家のおかみさんは、雨のしずくをポタポタたらしているお坊さんを、気のどくそうにみました。
「このさきに、とまれるとこがあるにはある、和尚(おしょう→詳細)さんのいねえ古寺だ」
旅のお坊さんは、それをきいて雨のなかを歩きだしました。
「あ、ちょっとまってけさえ」
おかみさんはお坊さんをひきとめると、にぎった焼きめしをひとつ、さしだしました。
お坊さんは、ずぶぬれになって、その古寺にたどりつきました。
草がおいしげったけいだいをつっきって、寺に入ったお坊さんはビックリ。
なかはいちめんクモの巣だらけで、かびのにおいのしみついた、とてもとてもひどいあれ寺だったのです。
「日のくれぬうちに、まずは、たきぎを」
お坊さんは、えんの下にたきぎをみつけると、いろりでもやしました。
お坊さんは、ぬれた衣をぬぎ、いろりの火にかざしてかわかすと、
「おお、そうじゃ。焼きめしじゃ」
お坊さんはおもいだして、焼きめしをほおばりました。
からだはあたたまり、ばんごはんもたべたので、お坊さんはそのままゴロリと横になると、グーグーとねてしまいました。
それから、どれくらいたったころか、だしぬけにガタン! とでかい音がして、お坊さんは目をさましました。
「ひどい音がしたようだが、なにごとか」
しばらくジッと耳をすましましたが、なにごともありません。
お坊さんは、火のきえかけたいろりに気づいて、たきぎを一本とりあげました。
と、そのとき、
キシッ、キシッ、キシッ、キシッ。
と、本堂のほうから、板の間をふんで近づいてくる音がして、やぶれしょうじがスーとあきました。
「なにもの!」
お坊さんは、サッと、たきぎを持ちかえると、かたひざをたてて身がまえます。
いろりの火が、ユラユラともえあがり、そのゆれるあかりのなかにあらわれたのは、灰色の着物にほっそりと身をつつみ、むねに赤んぼうをだいた女の人でした。
(こんなひどいあれ寺に、女がすんでおったとは)
と、さすがのお坊さんも目をみはりました。
女は、いろりのあかりをさけるようにうつむいたまま、す足でヒタヒタとお坊さんのそばにきて、ペタリとすわりました。
そして、力のない声でいいました。
「おねげえがあるんだけども。どうかひとばん、この子を、あずかってもらえんか。たのむから、わけはきかねで、あずかってくだせえ」
お坊さんは、どうせ今夜はとめてもらうのだし、よほどふかいわけがあるのだろうと、その赤んぼうをあずかることにしました。
「ありがとうございます」
女はれいをいうと、赤んぼうをころがすようにそこにおいて、たちあがりました。
しょうじがスーッとしまり、キシッ、キシッと、いう音が遠ざかっていきます。
するとどうでしょう。
今まで上をむいて手足をバタバタさせていた赤んぼうが、ゴロンと、ねがえりをうち、お坊さんのまわりでハイハイをはじめました。
それが、べつになにかをみつけてとりにいくというのでもなく、ただ、「ウバッ、ウバッ」と、かわいいひとりごとをいっては、一ど、二ど、三どと、お坊さんのまわりをグルグルまわりつづけるだけです。
「みょうな赤子(あかご)じゃ」
おなじところを、グルグルとはいまわる赤んぼうをみているうちに、お坊さんは、ふと、首のところをしめつけられるような気がしてきました。
その力が少しずつ強くなっていくようで、ふしぎにおもったお坊さんが、首に手をやろうとしたとたん、ギリギリギリと、ひどい力でしめつけてきたのです。
お坊さんは、くるしさに首をかきむしり、もがきながらも赤んぼうをみると、もう、はいまわることもなく、じっとこちらをうかがっているではありませんか。
「さては、ばけもの・・・」
と、さけぼうとしましたが、声がでません。
つぎのしゅんかん、バリッと音たてて、てんじょう板の一まいがはずれました。
そして、なんと赤んぼうが、スルスルとてんじょうにあいた穴にむかって、のぼりはじめたではありませんか。
「うっ、にがすものかっ」
お坊さんは、くるしまぎれにそばにあったたきぎをつかむと、力をこめてなげつけました。
「ギャーッ!!」
ひと声、ものすごいさけびがあたりにひびきました。
朝になって、きのうのお百姓のおかみさんが、だんなといっしょに古寺へやってきました。
「ゆうべは、すまんことしたなあ。ぶっこわれの古寺で、なんぎしていると、しんぱいでみにきたんだ」
そういうて、ふたりがあがりこむと、お坊さんは、いろりのふちに気をうしなってたおれていました。
「坊さま、坊さま」
と、ゆりおこされて、やがて気がついたお坊さんは、ふたりにわけをはなしてきかせます。
だんなとおかみさんは、お坊さんをたすけて、おそるおそるてんじょううらをのぞいてみてビックリ。
いちめんに、人の骨がちらばっており、かたすみの骨の山の上では、おそろしく大きなクモの親子らしいのがうずくまっています。
よくみると、親ぐもが死んだ子ぐもをかかえて、身動きひとつしないでいるのでした。
「そうか、夜中のばけものはクモであったか」
そのあと、お坊さんは村人にたのまれてその古寺の住職(じゅうしょく)になり、てんじょううらの骨を手あつくほうむりました。
そして、二匹の親子グモの死がいも、
「子を思うきもちは、人間もクモも同じ事。じょうぶつせいよ」
と、いって、ふかぶかと土にうめてやったそうです。
おしまい
| 子どもの病気相談所 |
| ・トップページへ |
| 病気の検索 |
| ・WEB問診 |
| ・カテゴリー別 |
| ・あいうえお順 |
| ・キーワード検索 |
| お役立ち情報 |
| ・緊急対応マニュアル |
| ・家庭のツボ療法 |
| ・病気を改善 料理薬 |
| ・病気を改善 お薬童話 |
| ・予防接種の豆知識 |
| ・安全な市販薬 |
| ・夏の虫さされ特集 |
| ・よくある質問Q&A |
| ・無料の電話相談リンク |
| 福娘のサイト |
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
| 福娘童話集 世界と日本の童話と昔話 |
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |