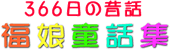| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 百物語の朗読 ・ 日本のこわい話(百物語) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 → 31話 〜 40話 → 41話 〜 50話 → 51話 〜 60話 → 61話 〜 70話 → 71話 〜 80話 → 81話 〜 90話 → 91話 〜 100話 |
| - 広 告 - |
百物語 第二十話
ヘビ酒をのんださむらい
むかし、伊原新三郎(いはらしんざぶろう)いうさむらいがおりましたが、徳川の世(江戸時代)になって、つかえる殿さまもなく、ブラプラとながれ歩いていました。
ある夏のこと、三河(みかわ→愛知県)へいき、三方が原(みかたがはら)というところへ足をのばしました。
そこは、武田信玄(たけだしんげん)の軍と、織田信長(おだのぶなが)の軍とがたたかった、名だかい古戦場(こせんじょう)でした。
あつい日ざかりをすぎ、ヒグラシゼミが鳴きだすと、夕風がまきおこって、すずしくなりました。
人っ子ひとりこない道を、どれくらいいったでしょう。
林があって、ひょいと木のあいだをのぞいたところ、むこうに、まだあたらしい家が四、五けん見えます。
しかも、たべものなどを売る店のようです。
「ここに茶店とはありがたい。ちと休んでいくか」
新三郎は林をくぐって、すぐ店のまえへでました。
すると、年のころ十四、五の、かわいらしいむすめがでてきて、
「おいでなさいまし。お武家さまが、いつも立ちよっていかれるお店でございますよ」
と、あいそよくいうのです。
いわれるままに、新三郎は店へ入って、こしをおろしました。
ほかには客がなく、店の人もいないようすでした。
「さぞ、おつかれでございましょうね。これをおめしあがりになって」
むすめは、もちをだしてきてすすめましたが、新三郎が、
「もちは一つでよい。酒はないか」
と、いうと、
「あら、気がつきませんでした。いいのがございますとも。すこしおまちを」
と、少しまたせてから、お酒をもってきました。
「・・・うまい!」
はらにしみわたるようなお酒でした。
しかも、そのむすめがなれなれしいしぐさで、おしゃくをしてくれますので、新三郎は二本三本と、とっくりをからにしました。
(よいむすめじゃ。しかし、このような場所に、むすめがひとりだけとは)
なにか、心にひっかかります。
新三郎もさむらいですから、すこしぐらいよったって、ゆだんはしません。
「あと、もう一本たのむ」
「かしこまりました。ただいま、すぐに」
むすめがおくへ酒をとりにいったとき、そっとついていって、台所をのぞきました。
そして、新三郎はおもわず息をのみました。
大きなヘビが一ぴき、てんじょうからつるしてあって、むすめは刀で、そのヘビのはらをさし、血がトクトクたれるのを、手おけにうけていました。
そして、血のなかへ、なにかわからないものを入れてかきまぜ、ニタッとわらったとおもうと、もう酒にしてしまいました。
(ただごとではないぞ!)
新三郎は、身の毛がよだつおもいで、店の外へととびだして走りました。
「お武家さま、おまちになって。・・・いまさら、おにげになるとは。・・・まて、まて、おまちなされ! ・・・またんか!」
あのむすめが、さきほどとはちがった声で、おいかけてきました。
そればかりではありません。
むすめの後ろのほうで、聞いたこともない、なん人かの声がして、
「せっかくのえものを、とりにがすなよ!」
と、こっちへやってきます。
ふりむいてみると、人のせたけの倍もある長いものが、ズリズリとおいかけてきているのです。
新三郎はいちど道まででて、また林へかけこみました。
「あいつめをとりにがしたら、あしたは、わしらにわざわいがおこるぞ」
「おう、にがしてたまるか」
と、わめきたてます。
えだにからまれ、草に足をとられ、それでも新三郎は、むがむちゅうで走って、やっと町はずれの民家にたどりつきました。
そこの主人は、わけを聞くと、いぶかしそうに首をかしげました。
「はて、あの林のあたりには、茶店どころか、家一けんございませんよ。きっと、ばけものどもに、さそいこまれなさって・・・。まあ、ごぶじでなによりでした」
「まさか? いや、めいわくをかけたな」
新三郎は、その夜は、とまっていた宿(やど→詳細)屋へもどりましたが、どうかんがえても、ふしぎでなりません。
あくる日、近くの男たちを集め、きのう酒をのんだ店を、いっしょにさがしました。
しかし、そのあたりには家一けんなく、草がボウボウとしげっているばかりで、人の足あとさえないのでした。
ただ、草のなかに手足の少しちぎれた、大きめのほうこが一つ、すてられていました。
ほうこは、はいはいをする幼児をかたどった、むかしの人形です。
「これが、十四、五の、あのむすめにばけたものか」
新三郎がつぶやくと、ほかの男たちのおどろく声がして、大蛇のむくろを見つけました。
長さが四、五メートル、色は黒く、おなかが切りさかれていました。
また、ちょっとはなれたところに、人のがいこつが三そろい、肉も皮もとけてなくなり、まっ白い骨だけになって、よこたわっているのでした。
ほうっておいては、なんのたたりがあるか知れませんので、新三郎は大蛇のむくろも、がいこつも、かたちをのこさないようにうちくだいたうえ、たきぎをつんで焼かせました。
そして、堀の底へしずめました。
ところで、伊原新三郎というさむらい、もともと病気がちでしたが、ヘビ酒をのまされたせいか、このあとはふしぎなほど元気になったということです。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |