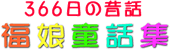| お話しの移動 |
| ・ 福娘童話集 ・ ジャンル別 ・ 日本のふしぎ話 (全50話) → 1話 〜 10話 → 11話 〜 20話 → 21話 〜 30話 → 31話 〜 40話 → 41話 〜 50話 |
日本のふしぎ話 第7話
クジラと海のいかり
むかしむかし、クジラとりの村で、長いこと不漁がつづき、村のみんなは困っていました。
そのころは、お百姓(ひゃくしょう→詳細)が米をねんぐとして代官所(だいかんしょ→江戸時代、地方をおさめた役所)などへおさめたように、そこの漁師たちも、クジラの肉を殿さまへおさめていたのです。
クジラがやってこなくては、ねんぐをおさめたくてもおさめられません。
ほんとうにこまっていると、ある夜、親方がふしぎなゆめを見ました。
紋付き(もんつき)の着物をきたクジラの親がきて、
「わたしらは、あす、熊野まいり(くまのまいり→和歌山県熊野三社へのおまいり)に、子クジラをつれて、この沖を通ります。どうか、こんどばかりはお見のがしください」
と、熱心にたのむのです。
親方は、熊野まいりだというので、
「よろしい。あすは船をださん」
と、かたくやくそくしました。
つぎの朝早く、山の見はりに、あいずののろしがあがりました。
「クジラがきたぞ!」
と、漁師たちは小おどりして、浜へいそぎました。
親方はおどろいて、「船を出すな!」と、とめましたが、みんなききません。
ゆうべのふしぎなゆめの話をすると、漁師たちはわらって、つぎつぎに船をこぎだしました。
しおをふきあげ、沖にすがたをあらわしたのは、子づれのセミクジラでした。
このセミクジラが、いちばんお肉がおいしく、お金ももうかりました。
親方とのやくそくを信じきっていたのか、船が近づいてきても、セミクジラの親子は、ゆうゆうと泳いでいきます。
やがて、漁師たちの船は、親子クジラをとりまき、親クジラの頭にアミをかけました。
ハザシとよばれる漁師が、船をこぎよせ、一番モリを親クジラにうちこみました。
そのとたん、おこった親クジラは、おそろしいいきおいで、漁師たちの船におそいかかりました。
ふかくもぐったかとおもうと、たちまち山のような巨体をあらわして、漁師の船を空へもちあげ、また、つよい大きな尾で、べつの船をこっぱみじんにたたきわりました。
しかも、空がにわかにくもり、すみをながしたように、まっくらになったのです。
「シケがきたぞ。つなを切れ」
漁師たちが気づいたときは、おそすぎました。
突風がふきだし、海はあわだって、二、三十そうもの船は、かたっぱしから波にのまれていきました。
ぶじに浜へもどることができた漁師は、ひとりもいなかったそうです。
そして、このことがあってから、
「セミ(セミクジラ)の子づれは、ゆめにもみるな」
と、どこの浜でもいわれるようになったのでした。
おしまい
| ジャンルの選択 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 福娘童話集 人気コーナー |
|||||||||||||||||||||||||||
| きょうの新作昔話 未公開の童話・昔話を毎日 一話ずつ公開 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おはなし きかせてね 福娘童話集をプロの声優・ナレーターが朗読 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 小学生童話 幼稚園から小学6年生まで、学年別の童話・昔話集 |
|||||||||||||||||||||||||||
| おくすり童話 読むお薬で、病気を吹き飛ばそう! |
|||||||||||||||||||||||||||
福娘の姉妹サイト http://hukumusume.com |
|||||||||||||||||||||||||||
| 366日への旅 毎日の記念日・誕生花 ・有名人の誕生日と性格判断 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 世界60秒巡り 国旗国歌や世界遺産など、世界の国々の豆知識 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 子どもの病気相談所 病気検索と対応方法、症状から検索するWEB問診 |